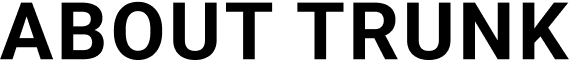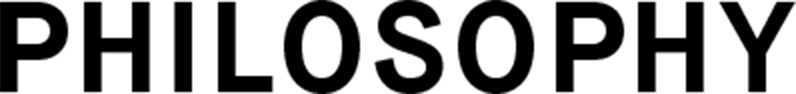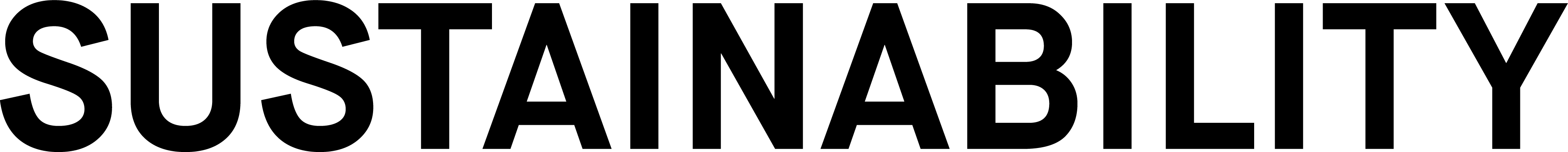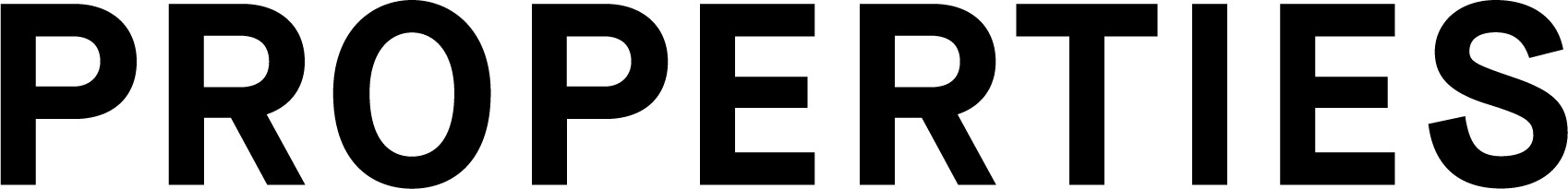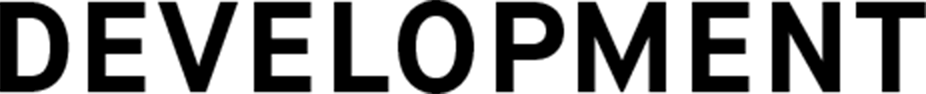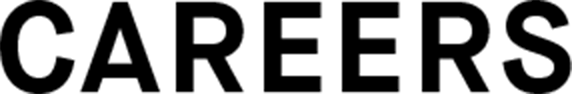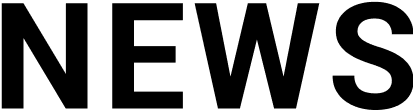TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKのオールデイダイニングであるPIZZERIA e TRATTORIA L’OMBELICO(ピッツェリア・エ・トラットリア ロンベリコ)。代々木公園の豊かな緑を眼前に望む井の頭公園通りに面し、宿泊者はもちろん、高感度なライフスタイルを求めるゲストたちを日々お迎えしています。薪窯で焼き上げるナポリピッツァをはじめ、クラシックな伝統料理が楽しめるオーセンティックなこのトラットリア(家庭的な雰囲気を湛えた、誰もが気軽に立ち寄れるイタリア料理店)で、本場ナポリ仕込みの知識と技術を駆使してピッツァ周りのすべてを取り仕切るのがピッツァイオーロ(ピッツァ職人)の森山伸也(もりやま・しんや)。TRUNKでは社員一人ひとりがやりたいこと、叶えたいことをWANTとして掲げ、その実現を後押しする文化が根付いています。誰かが心に抱いた小さなWANTから新たなプロジェクトが生まれ、その想いに共感した仲間が集まることで大きなうねりとなっていく。WANTから始まった「新しい灯」が、TRUNKにはあふれています。彼が叶えたWANTは、解決が求められる社会課題のひとつとして関心を集める「子どもたちの食環境の改善」。いわゆる「子ども食堂の支援」です。「誰かのためになることが、結果的に自分のためになると思って、できることに取り組んでいる」と語る森山。謙虚でありながら強い意志を感じさせる職人の声に、共に耳を傾けてみましょう。
きっかけはソーシャライジングへの共感。
ピッツァ職人としてTRUNKに加わる。
TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKのPIZZERIA e TRATTORIA L’OMBELICO(ピッツェリア・エ・トラットリア ロンベリコ)でピッツァ職人として働いています。都内の複数レストランで経験を積んだ後、ナポリでの修行を経て、2023年9月、TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKの開業に合わせてTRUNKに加わりました。
サーフィンをやっていることもあり、地球環境に対する意識は人よりも強いものがあったと思います。そこで知ったのがTRUNKの掲げる「ソーシャライジング」という考え方。「ENVIRONMENT(環境)」「LOCAL FIRST(ローカル優先主義)」「DIVERSITY(多様性)」「HEALTH(健康)」「CULTURE(文化)」など、さまざまな視点で社会に貢献できるのであればぜひ働いてみたい。そうした想いからTRUNK(HOTEL) YOYOGI PARKのオープニングスタッフの一員となりました。
新しい仕事先を探すなかでこだわった点は二つ。一つが「本格的な薪窯があること」、もう一つが「ピッツァ職人というポジション」でした。イタリアでの修行の成果を活かすには本場にも劣らない薪窯が欠かせず、ピッツァを極めるのであれば何でもつくる料理人としてではなく専門職として働きたい。TRUNKはその両方を受け入れてくれました。

32歳、ナポリへ。
本場で得た知識と経験が、今を支える。
この仕事に就くまでにはいろいろな仕事を経験しましたが、26歳の時にピッツァに出会い、その深遠な世界を知れば知るほど「この道を極めてみたい」と思うようになりました。持ち前の探究心に火が着いてしまったんですね。
ピッツァの本場であるイタリア・ナポリで修行を始めたのが32歳の時。今でこそ、外国からの旅行者が「日本を訪れた時に食べたいもの」としてピッツァを挙げるほどに、日本におけるナポリピッツァは年を追うごとにそのレベルを高めてきていますが、その頃は日本で本場のナポリピッツァを学べる店は僅かしかありませんでした。年齢も決して若くはなかったので、限られた席が空くのを待つより本場で学んだ方が早いと思ったんですね。「だったら最初からメジャーリーグに行ってやろう」という気持ちでしたね(笑)。
僕が修行させていただいた「ピッツェリア・スタリータ・ア・マテルデイ(Pizzeria Starita a Materdei)」はナポリの中心地から少し離れたマテルデイ地区という住宅街にあるピッツェリア。ピッツェリアはイタリア語で「薪窯や石窯を備え、ピッツァを専門に提供する飲食店」を意味し、特にナポリのピッツェリアはレベルが高いことで知られます。そのなかでも、スタリータは1901年創業と120年以上の長い歴史を持ち、地元の人たちに愛される伝統的なナポリピッツァの名店に数えられます。ヴィットリオ・デ・シーカが監督し、トトやソフィア・ローレンといった往年の名優たちも出演した1954年公開のイタリア映画「ナポリの黄金(L’oro Di Napoli)」の舞台にもなりました。この店のボスはローマ教皇にピッツァを献上するほどの高名な職人で、「この人の下で真のナポリピッツァを学びたい」と思ったのがきっかけで、スタリータでの修行を決意しました。
スタリータのことは知人から聞いていましたが、誰かからの紹介があったわけでもありません。現地の仲介業者は「店にあなたが行くことは伝えてあるし、宿泊先も確保している」と言っていましたが、まぁ、そこはイタリア、行ってみたら何も話が通っていない状況で、いきなり彼の国の洗礼を浴びました(笑)。仕方がないので直接店を訪ね、「ここで働かせてください」とお願いしましたが、もちろん最初は取り合ってくれるはずもなく、そこから数時間、粘りに粘った結果、「明日から来られるか?」と。きっと覚悟を試されていたんだと思います。
それから最初の3ヶ月間は給料なし、休みなし。その期間も、やらせてもらえたのは仕込みだけでした。今にして思えば、まずは店のスタッフたちとどれだけ馴染めるのかを測っていたんですね。僕はイタリア語もわからないのですが、とにかく自分から積極的にコミュニケーションを取るようにしました。日本人にありがちな控えめな姿勢では全く相手にされませんからね。時には彼らと喧嘩もしながら関係性を築き、徐々に店の一員として認めてもらえるようになりました。そこからは任される仕事も増えていきましたね。スタリータで過ごした一年間で学んだ知識と技術が、今でも間違いなく僕を支える基盤となっています。

シンプルでありながら、極めるのは至難の業。
奥深きピッツァの世界。
ピッツァの世界は実に繊細で、どこまで行っても極めることができない奥深さがあります。
ピッツァの生地は、小麦粉、塩、水、酵母という4種類の材料だけでつくられる、実にシンプルなもの。それなのに明確なレシピが存在しないのは、その日の気温や湿度によって微妙な調整を加えなくてはならないからです。また、発酵という過程が加わることで生地の状態は時々刻々と変化していくため、どうしても長年の経験が求められます。丁寧に教えてもらったからと言って、誰もがすぐにできるものではないのです。
ピッツァの仕事は「感覚的なものづくり」です。たとえ同じ店の、同じ窯で焼いたピッツァでも、焼き手が違えばその味や食感にも微妙な違いが現れます。薪窯には温度計も設置してありませんから、すべては職人の感覚次第。イタリアでは、「自分の好みの焼き手がいる時を狙って来店する」という人も決して珍しくありません。「生地が命」と言われるナポリピッツァは、それほどまでに焼き手の個性が現れる料理なんです。面白いですよね。
L’OMBELICOではスタッフの教育にも携わりますが、「生き物」を相手にするような仕事なので、いくら数値化し、マニュアル化して教えたとしても、同じピッツァ生地が作れるようにはなりません。そこが難しくもやりがいのあるところですね。一昔前であれば「俺の背中を見て覚えろ」という職人も多かったですよね。と言うより、それが普通でしたし、僕がイタリアで学んだ時もそうでした。ただ、時代は移り変わっています。今は「感覚的な事象を言語化して伝えること」が求められていると感じます。言葉にして伝え、相手が理解した内容も言葉で返してもらう。そうしたやりとりを経て、自分が持っている知識と技術を教えることを心がけています。
そして何よりも大切なのが「挑戦する場」を用意すること。完璧にこなせないにしても、その人が持てる「今の100%」を出し切る機会を与え、もし足りない部分があれば黙ってフォローする。それが教える側の責務です。日々、挑戦できる環境に身を置くことで、経験を積みながら成長していくのだと考えています。

子どもたちの笑顔があれば。
WANTを実現した「子ども食堂」の取り組み。
世のため、人のために生きる。これは僕自身がいつも大切にしていることです。「誰かのため」にやったことがいずれは「自分のため」になると信じているので、いつでも「誰かのためにできること」を探しています。
僕がWANTとして掲げた「子ども食堂の支援」も、「誰かのため」と考えて行き着いたテーマです。この取り組みの背景には、社会貢献への関心はもちろんですが、TRUNKが大切にしているソーシャライジングの考え方をより広めていきたいという観点も含まれています。上司と話すなかで「子ども食堂にL’OMBELICOのピッツァを寄付したい」と申し出たところ、渋谷区役所でこどもテーブル(渋谷区版の子ども食堂)に関わっていらっしゃる担当者につないでもらい、関係各所との調整を経て実現へと漕ぎ着けました。
渋谷区内のこどもテーブルを利用するのは、食べること自体に窮しているというケースはほとんど見られません。一方で課題となっているのが「孤食」です。両親が共働きで、夕食はいつも一人でコンビニエンスストアのお弁当を食べている。そうした子どもたちが少なくないという現状は、やはり寂しいものがありますよね。僕自身、三児の父親なので、毎日のように一人で食事をする子どものために何かできないかと考えて、この取り組みを始めようと思い至りました。
子ども食堂には、L’OMBELICOで前日に余った生地を活用したピッツァを提供しています。僕の主な業務は、渋谷区役所や寄付先となるこどもテーブル運営者との調整です。実際にピッツァを作り、冷凍保存し、再加熱して施設に届けるという実務部分は、この活動に賛同してくれたTRUNKの仲間たちが担ってくれています。また、この取り組みは多くのピッツァをつくれる貴重な機会でもあるので、若手スタッフの教育の場としても活用させてもらっているという側面もあります。
フードロスを減らし、スタッフの技術教育にも役立つこの取り組みを、2024年の夏以来、月1回のペースで続けてきています。提供先は毎回異なるので、事前に訪問して施設の状況や設備を確認することは欠かせません。場所によっては一度に50人ほどの子どもたちが集まるので、TRUNKの仲間たちに助けてもらっていますね。声をかければ快く引き受けてくれる仲間がいることは、本当に心強く思います。取り組みを進めていくなかで改善点も見つかって、少しずつ進化も遂げています。例えば、ピッツァを運ぶ箱。最初はダンボール製のものを使っていたのですが、リユースできる専用ピッツァボックスに変更し、資材ロスも最小限に抑えるシステムに変更しました。そのボックスは結構重いので翌日は筋肉痛になってしまうんですが(笑)、ピッツァを食べてくれた子どもたちの最高の笑顔があるから少しくらい大変でもやっていけますね。「美味しい!」と言って食べてくれる瞬間が何よりの喜びです。

WANTは、自分の内側から湧き出るもの。
食を軸に、新しい挑戦を続けていきたい。
僕にとって幸福なのは、「自分が大切にしたいと考えている生き方」と「ソーシャライジングの考え方」が重なっていること。「誰かのため」にやったことがいずれは「自分のため」になると信じているので、自身のライフスタイルと会社の目指す方向性が合致しているのは幸せなことです。「WANTとして掲げたから」という外的な理由で取り組んでいるわけではなく、自分の内側から湧いてくる「やりたいこと」や「なすべきこと」を考えていたら、自然とWANTが叶っていたという感覚です。
今は提供先の施設にピッツァを届けている形ですが、いつかはL’OMBELICOに子どもたちを招き、食育を兼ねたワークショップなどもやってみたいですね。僕らがつくったピッツァを食べてもらうだけでも十分役に立てていると思いますが、子どもたち自身がピッツァをつくる機会を持てたら、また新しい展開が待っているのではないかと思います。この子ども食堂の取り組みを一歩ずつ発展させ、いずれはTRUNK(HOTEL)全体としてのプロジェクトにまで成長させられたら嬉しいですよね。
食というテーマで言えば、個人的には「狩猟」や「コンポスト(家庭や施設から出る生ごみなどの有機物を微生物の力によって分解して堆肥にすること)」にも関心を持っています。自ら獲物を仕留めることで、命をいただくことの価値を改めて実感する。ホテルから出たゴミを分解した堆肥を使って屋上の自家菜園で野菜を育て、その野菜を使った料理をゲストに提供する。そんな、まさにソーシャライジングを体現した新しいサイクルをつくれたら面白いですよね。子ども食堂の次のWANTとして、そんな野望を持っています。仕事、家族、そして少しの趣味。個人的にはその3つのバランスを大切にしながら、これからも食を軸とした新しいチャレンジも続けていきたいですね。